さてと・・・石峰優璃はパソコンの電源を落とす。
その瞬間、この救急科のリハビリテーション室もまたひっそりと寝息を立て始める。そんな気分になるけれど、しかしどこか遠くでサイレンの音は反響している。
石峰は、デスクの引き出し奥にある古ぼけた日記帳を取り出した。
日記なんて習慣がついたのは一体いつ頃だろうか。
それは思い出しても不思議と思い出せなかった。
部屋に積まれた日記帳を探ってみれば分かるとは思うが、
どうしてもそんな気にはならない。過去を振り返るのは嫌いだからだ。
矛盾しているな。と石峰は片方の唇だけを上げて笑みを浮かべる。
そして今日の出来事を緩やかに脳裏に描き出す。
あの新人君は頭から湯気を出しそうになりながらフラフラと帰っていった。その光景を思い出すとなんだか楽しくなるのを感じた。
もちろん新人いびりをしているつもりではない。
ああいう風に話せる新人は、もとい他のセラピストを思い浮かべたとしても少ないと思う。
私は人とは違うからな。だからこそ似たような人を見ると妙にはしゃいでしまう。
悪い癖だと石峰は思う。
そしてその結果、その友人をもまた失っていくからだ。
人に流れる時間は平等のようで、その実流れる速さには明確に差があると思う。
同じように歩んでいたとしても、いつしかその姿は遠くなり、自分の遥か後ろに消えていく。
結果独りとなるのだけれど、それもまた心地良いから困りものだと思う。
正直集団の中は苦手だ。だけども賑やかなのが嫌いなわけでもない。
その中で楽しめないのはきっと、その浮ついた気持ちが恐ろしいからだと思う。
それが失われた瞬間、途方も無いほど自分がこの世で一人に感じてしまう。そしてその一人で居る時間の方が、慣れているからか心地良く感じてしまう。
人の産まれは変えられない、今まで生きてきた時間もまた不変だ。
だからこそ、こういう風に日記をつけているのかもしれない。
自身の行動の原理などは何とでも理由は付けられるけれど、その実その本態は言葉にすることはできない。残せたとしても結局は後付けや言い訳にも取れてしまう。
誰かの中に何も残せない事は分かっている。自分が消えた瞬間、私という存在は有象無象の中に紛れてしまし、そして程なくして消え去ってしまう。
結局のところ私という存在を残したいという、浅はかな動機なのかもな。
そう思いつつ石峰は今日の事を日記に記す。
またあの新人は自分に話しかけてくるのだろうか。
そうでなくとも、まぁ使えるようには仕上げなければならない。
さもなくばそれで割を食うのは患者様なのだからな。
そうとだけ考えて石峰は日記を閉じる。
今度はあの新人君とどんな事を話そうか。
らしくも無いな・・・とは思いつつ石峰はそんな事を考えた。
黒い犬が駆ける姿が描かれたマグカップは、両手の中で湯気を立てないくらいの程よい温度で、その存在を明らかにしていた。
【これまでのあらすじ】
『内科で働くセラピストのお話も随分と進んできました。今まで此処でどんなことを学び、どんな事を感じ、そしてどんなお話を紡いできたのか。本編を更に楽しむためにどうぞ。』

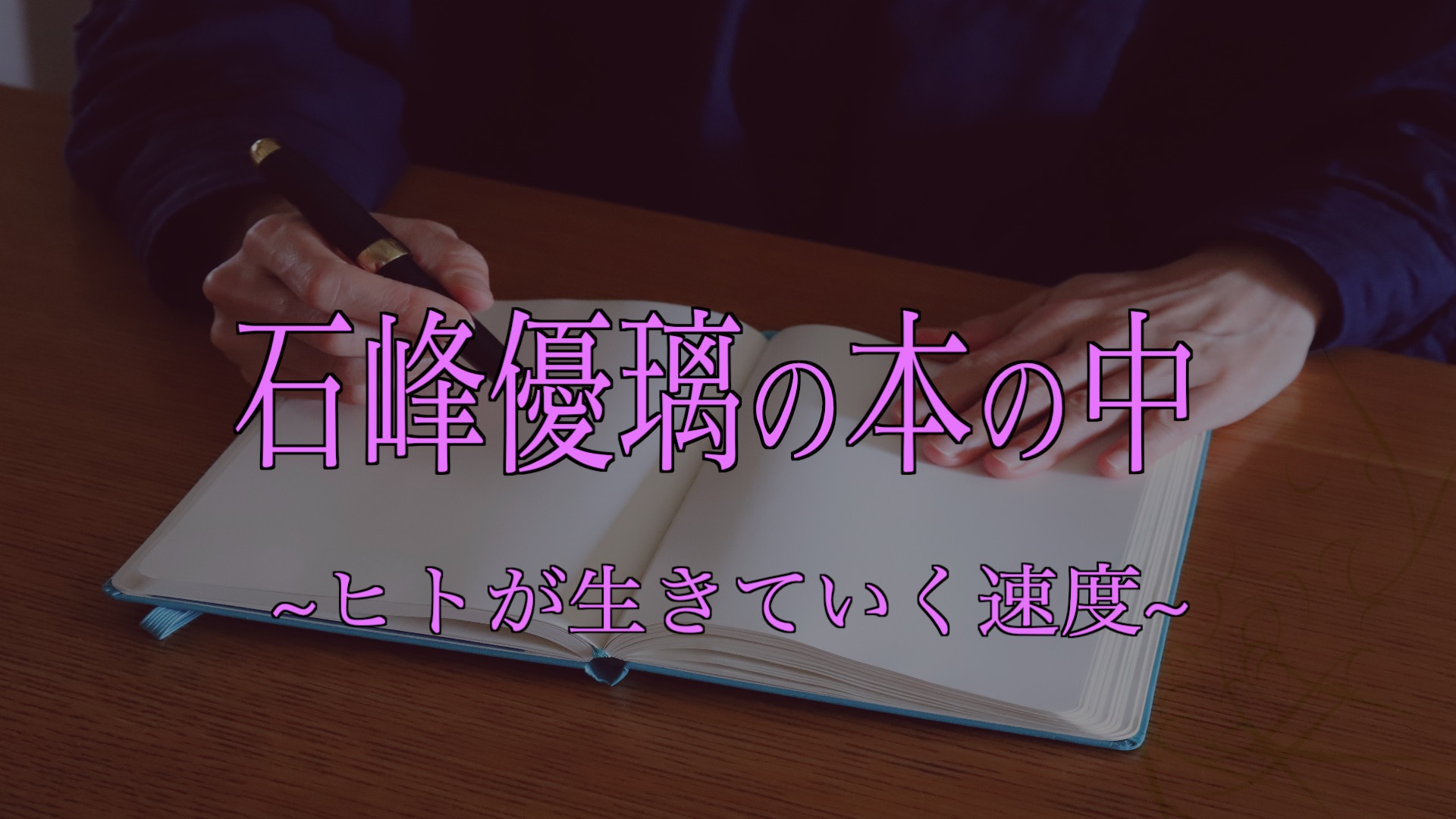



コメント